 |
酒 役 づ 人 く の り 監 に 督 |
江戸時代には交野のどの村でも一、二軒のつくり酒屋がありました。当時幕府から厳しく規制され、また役人の監督も受け、米の豊凶によって割当が増減されたといいます。 |
 |
縄 遺 文 跡 の 豊 神 か 宮 に 寺 |
神宮寺には交野山の登り口に約一万三千年前の旧石器時代、それより200メートル下ったところに約九千年前の縄文時代早期の遺跡があります。特に底部の尖った押型文の神宮寺式土器は、縄文時代早期を代表する土器の一つとして有名です。 |
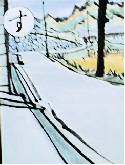 |
す
そ
を
山 め
の ぐ
根 る
の は
道
|
古代の河内の中心である国府(こくふ)(柏原の国分)に至る南北道として山の根(やまのね)の道がありました。 |
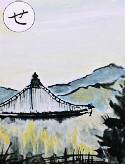 |
千 亀 手 行 山 寺 在 上 は 所 皇 |
千手寺(せんじゅじ)は今は廃寺となりましたが、亀山上皇が病気の時、獅子窟寺の薬師仏に祈願され、ここを行在所(あんざいしょ)として千手観音をまつって寺とされました。 |
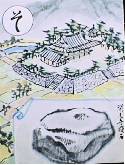 |
礎 石 に 開 し 元 の 寺 ぶ |
昭和29年神宮寺で天平時代に礎石が発見され、古代当地方に栄えた大寺の果てだとわかりました。 |