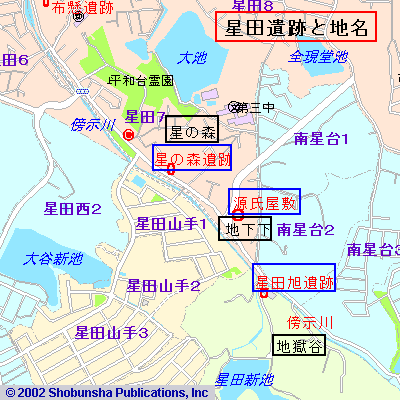|
�@2002.10.5�i�y�j�V������A�Q����10�l�B���h�[�����X���߂��Ԃŏo���A���c��قŘa�v�c�搶�Ɨ��������A���c�n������ē��������B
�@����́A�����A�����j���N�E�H�[�N���ē����Ē����Ă��镽�c���A�����̘b�͂Ȃ�ł����H�i���j���N�E�H�[�N�i���c�n���� �P�O�^�T �j�ɓ����̎U����ڂ������e�����܂����̂ŁA����Ȃ�����p�����Ē����܂����B
�@�H����̒��A���c�n�������܂����B
�}����A�a�v�c����ɐ����������肢�����c��قɏW�����܂����B���̉�ق������r�̂����Ɍ��Ă��Ă��܂��B�r�̒z���N��͕s���ł��邪�A���c�̒r�̒��ł͍ł��Â��A�V�{�R�̕����r�Ƃ��Ă���ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�܂��A�r�̒��ɓ��������āA�ٍ��V���J���Ă���B
��쒬�j�Ɂu���������̉��A�R�̒����ɕٓV�Ђ������āA�����r�̒[���璹����������A�Βi��o���ĎQ�w���Ă������A�]�ˎ��ア�̂��납�A�R������A�ٓV�ЂƂƂ��ɖ����r�̒��ɗ����ď������o�����B���̌ケ�̏����ɕٓV�Ђ��܂邱�ƂƂȂ����B�v�ƋL���Ă���B
�@�����ĉ�ق��o���Ƃ���A���쉈���ɐ������������Ƃ̂��ƁB�����ď㗬�Ɍ������ĕ����ƁA���R����������Ƃ���ɉ��̐��Ԃ��������B���̐��Ԃ�����Ƃ������Ƃ͏�̐��Ԃ�����Ƃ������ƁA�Õ����ɂ��Ɖ��̎Ԃ܂łQ�R�ԁi�S�P�b�j�Ƃ���B���a�P�O�N���܂ʼn���Ă����Ƃ̂��ƁB
�@���쉈���ɂR��̐��Ԃ�����Ă����̂��Ȃ��Ƌ����[���������Ă����������B�����Č��s���ň�ԑ傫�Ȓr�A���c��r�ˌ������~�˒n�����i�������j�ˈ��ꕶ��Ձː��̐X�i�����R�E���ю��E���̐X��3�ӏ��ɐ��~�����j�u�����O�������~��v���̏ꏊ�ɂ͂T�~��������ԑ傫�����܂�A���ƂS�͖��߂��Ă���Ƃ̐��������B
�@�r���A���n�̗O�����ł̂ǂ�������J��̑�t���܂ŁB�����œ�����X���ƎR�����Ƃ���������B
�@��J�k��t���Ő܂�Ԃ��A������̒����R���������ɑ���i�߂��B�z����Ձi���Ί�j�ˍ����ˑ啪���i��r������o�����p���������ŕ��ʕ����������j�ː��c����ɓ����B��Q���Ԕ��̃R�[�X�ł������B
�@�V�{�R���{���̃R�[�X�ɂȂ��Ă������A���Ԃ̓s���A����̗��j�U���ł��肢���邱�ƂŏI�������B
�@�a�v�c����̌����M�S���Ƃ����A�����Ƃ����A���C���Ƃ����A���������y�j�ɂ������M�̋����Ŋ���������ł����B�n���ҁA�n�܂����Ƃ���ł��B
�@�䂪�ӂ邳�Ƃ̒n�������ꂩ��������܂��B
�@
�@�@�����̏H�̔����A���c�̗��𐅎ԐՒn�A��r�A����ՁA���̐X�A�R���X��������S�s���܂Ŋy���B�@
�@�a�v�c�搶�̏ڂ������������c�̌Â����j�ƕς��s�����̎p�Ŋ������A�y�������j�E�H�[�N�ł����B
�@���y���݂ł���B��l�ł������̎s���̕��X�ɂ��̊�т𖡂���Ă������������Ǝv���܂��B
�@����Ƃ��A�F����U�������ĎQ�����܂��傤�I�I�I
�s�~�j�K�C�h�t
���c��r
�ʐς�3.9�w�N�^�[���ƌ��s�ň�ԑ傫���r�ł���B�r��1/3�����ߗ��Ă����R���̕~�n�ɂȂ��Ă���B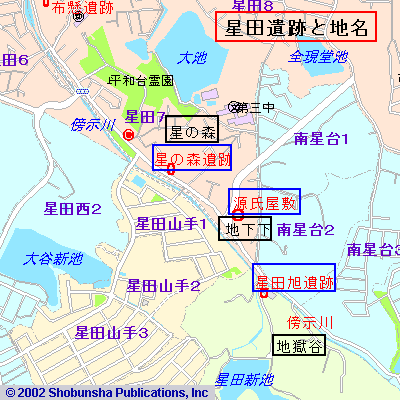
���̖ʐς͂U�w�N�^�[���قǂ������B���c��r�͍����Ə|�E������̋u�˂ɋ��܂ꂽ�L���J�n��������h��z���ĉ��~�߂��đ���ꂽ�l�H�̒r�ł���B�����z�����ꂽ���͕s���ł��邪�A�ËL�^�ɂ��ƁA���\�P�P�N�i1698�j�ɒ�h�̉��C���s���Ă���̂ŁA�����Â�����o���Ă������ƂɂȂ�B
�������~
�@�����̈ꓝ���c�����n�����ɏZ��ł��������A�������~�Ƃ����B
�u�����A���c���Y�E�q�吳��́A�͓������c������N����B�Ɩ�ۂɎO���A���ԁB��P�掟���A��]�˂ɋA��v
�@��P�̎掟���Ƃ��đ���ɏo�d���A���a���N�i1615�j��㗎��̂Ƃ��A���E�o���č]�˂ɋA������P�ɐ��s�������m�̒��ɁA���c���Y�E�q�吳�킪�����B
���݂͐��c�R������V�����J�ʂ��āA�T����̎�O�̐M���t�߂ł���B
�z������i�̂������������j
�@���a�T�S�N�Ɉ����w�Z���ׂ̓d�d���ЎБ�ݗ\��n������Ί펞��̐Ί�i��P���T�O�O�O�N�O�j�����@���ꂽ�B
���c�����
�@��J������T������㗬�ւP�L������s���ƁA�֎q�i�Ȃ��т����j�̒J�ƕ���i�ڂ��āj�̒J���痎����J��ƁA�n���J�̒J��Ƃ���ɏW�܂�Ƃ���A�������Ƃ����ė����̒J��ɋ��܂ꂽ�[�̏����ȑ�n�ɁA�ꕶ����̒����A������4�琔�S�N�O����l���Z��ł����B
�@�吳�̏��߁A���c�V�r���z�����ꂽ�Ƃ��A��ɋ߂��R�[�ŏ\���̒G�����Z���Ղ��������ꂽ�B���̏Z���Ղ���́A�L�k�ɓ��ꂽ��2000�N�O�̒����̐V�̎���̐��݂����@����Ă���B�܂��A�V�r�̒��ɒ���ł���R�̍肠���肩��a���J�ݓ���̚₪�o�y�����B
���݂͘V�l�z�[���������Ă���B
�s�~�j�K�C�h�t
���c�n��E�n���̗R���@���̂ق��̏������ɂ��Ă���������Q�Ƃ��������B
| ��(������) |
�@
����O���w�Z�̕~�n�́A���̐��k�ɍL���鐯�c��r�̔����ߗ��Ă�ꂽ ���̂ł���B�u���v�̒n��́A���c��r���قƂ�ǂ��߂Ă���B ���̂ł���B�u���v�̒n��́A���c��r���قƂ�ǂ��߂Ă���B
�����A�T����̓쑤�ɐ��c�V�r�Ƃ����傫�Ȓr������B���̒r�̓��암�Ɂu���v�Ƃ����n���������āA��ђn�̂悤�ɂȂ��Ă���B
�@��ђn�̕��̈���T����̗�����u���ꕶ��Ձv������A�ꕶ����̈╨���o�y���Ă���B�ꕶ����̐l�X�́A���̖T����̕ӂ�ɏW�����c�݁A��A�̏W�����𑗂��Ă����B���c�n��ł̍ŏ��̏Z�l�ł͂Ȃ������낤���B
�@���c��r�̒�h�ɗ��ƒ������L���L���Ɛ��ʂɏƂ�P���Ă���B�m���ɒ����̕����ɂȂ�B��h�̉��͌�_�A�z���Ɣ_�k�n������B������q��Ŕ_��Ƃɏo��B���̏�i��n���ɕ\�킵�����̂ł��낤�B
|
���m�X
(�ق��̂���) |
�@���A�����̓��A�T����ɖʂ����ꏊ���u���̐X�v�ł���B
���̐X�Ƃ����Ă��A�Z����i�ݐX�͂����킸���ł���A���̐̂��̐X�̒��ɐ���_�̂ɂ����Ђ��������B
�@���̎Ђ̗R���͂����ł���B
�@��������̏��߁A����V�c�̎���A�O�@��t�����s�̎��q�A���ɂ������Ă���ꂽ�B
�@����Ȃ�����A�����R�Ɛ��c�̌��ю����̐X�̂R�����Ɏ��j�����~���̂������Ƃ����B������@�Ƃ��āA���̂R�����̗��Ƃ��ꂽ�Ƃ����̂ł���B���c�̐l�X�́A���̍~�肽�R�����͂��ꂼ��̋�������W���ł���̂Łu�����O���ɐ����~��v�ƌ����Ċ�сA���c�̒n���́A�������琶�܂�Ă������̂��ƌ����Ă���B
|
���P��
(����������) |
�@
�@�n�����A�|�̕�����k���L�т�u�˂������܂ł��Ă���B���̓r���ɂ���n�����u���P��v�ł���B���c���w�Z�̓쑤�̓������P��ŋu�˂��ʂ��ɂ��ĉz���A�����̌���A�����A�R�J�ւƒʂ���B
�@���P��͋u�˂̎Ζʂ��Ӗ����Ă���Ǝv���邪�A���̒n���Ɂu�L���J�W�v�Ƃ����̂�����B���́u�J�W�v�Ɓu���v�A�n�`�I�ɂ悭���Ă���B���̏ꍇ�A�T������̒J�̏o�����ŁA�܂��A�Z�g�_�Ђ̐X������B�J�����������낵�Đ_�Ђ̐X��h���Ԃ�B���c�̏ꍇ�A�����̕����猩��Ƌu�˂̔�����Ζʈ�ʂɒ|�т�������A�T����̒J�A�����A�R�J�̒J�𐁂����ɒ|��G�ؗт̂���������Ƃ�������i�͂悭�����B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���|�т�G�ؗт𐁂������镗�̂���⓹�Ƃ������Ӗ��ŁA�u���P��v�ƕt����ꂽ�ƌ�������ǂ��̂ł͂Ȃ����B�z����L�т�u�˂̖k�̒[���������P��ł��邪�A���̋u�˂͓삪�����A�k���Ⴍ�Q�i�ɂȂ��Ă���B�_�{�R�ƌĂ�Ă����̍����i�̕����u�����{�Ձv�A�k�̒Ⴂ�i�̕����u�������@�Ձv�ƌĂ�Ă���B
|
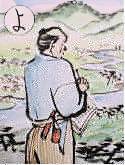
�@�]�ˎ��㒆���A�V���W�N(1788)�A���S���c���ɐ��܂���ɏZ���g�c�������Ƃ����l�������B�ނ͗���̓y������s�ɑ��A���h���Ƃɑ���ӌ������o���Ă���B
�@����ɂ��ƁA����ɒ����V��삪���c�ʂ��2��������V���ƂȂ��Ă��邽�߁A���̓V���ɒ������̏��͐�����l�ɐ��c�ʂ��������Ȃ��Ă���B���̌��ʁA�������̒�h���������Ă��㗬���痬��o��y�����쏰�ɂ����ς���̂ŁA�쏰�ʂ̏㏸�ƒǂ����������ɂȂ邾���ł���B���{��͓y�����ɗ����Ȃ�������u���Ȃ���Ή������Ȃ��̂ł���B
�@�g�c�������́A�y���̋������ł��鐯�c�̉��R��т̂͂��R���Ȃ������Ƃł���A���̂��߂ɎR�S�̂ɐA�т����āA����������~�߁A�R�S�̂�X�тŕ��������悤�ɂ��ׂ��ł���B��������Α�J���~���Ă��^���ɂ͂Ȃ炸�A���������ēy���̗��o�����Ȃ��Ȃ�B���R�����͂��ꂵ���Ȃ��Ɛ����Ă���B
�@�g�c�������@���{�ɐi���@�Ɓu��삩�邽�v�ɉr�܂�Ă���B
|
���n�i���킶�j
|
�m�{�̓��A���傤�Lj��]�J�ƍ����J�ɕW���V�O�`�W�O�����炢�̋u�˂��o�Ă���B���̊Ԃ̒J�ƒJ���o����n��̓y�n���u���n�v�ƌĂ�ł���B
�@�u����(���킢)�v�Ƃ����̂́A�ł��A���킲�킷��Ƃ������Ӗ��ł���B���C�̏��Ȃ��ł��߂̂��т��u���킢���сv�ƌ����A�Ԕт̂��Ƃ��u������v�u����߂��v�Ƃ������A���́u���킢�v�́A��������ł��Ƃ����Ӗ��ł���B
�@�u���n�v�́A�S�y���Ŋ�Ղ���܂ŏオ���Ă���ł��y���ł��������Ƃ���A�k�삷��̂ɔ��ɍ��̐܂ꂽ�y�n�A��J�����y�n�Ƃ����Ӗ������߂ĕt����ꂽ�n���ł��낤�B |
|