2003.7.26 第51回
交野歴史健康ウォーク
2003.7.26 第51回
![]()
![]()
![]()
|
(とき)平成15年7月26日(土)曇り後晴(気象庁が梅雨明け宣言) |
星田新池は交野市内で4番目の大きな池である。面積は2ヘクタールで、つくられたのは明治末から大正にかけて下の方の田んぼの用水として大切な役目を果たしている。
堤防の老朽化とともに大阪府が中心となって改修工事がなされ、昭和60年3月に完成した。 今、新池公園となりその広場に改修記念碑がたてられている。
この堰止めに使われた土砂が傍示川との間にあった「旭の山」である。この山をそっくりとって、巨大な高い堤防になっており山の跡地には老人ホームが建てられている。取り去られた「旭の山」は縄文遺跡でもあった。また地獄谷とぼって谷との合う所では土器に入った和同開珎が発掘されている。このようにこの旭の山地区は古代縄文時代から弥生、古墳、奈良時代を星田に住んだ先住民の生活の場であった。 星田新池の上流の谷は(地獄谷・なすび谷)と(ぼって谷)という。
その谷川が一つに集まるところに星田新池があり、そこに交野最古の人が住んでいた。(旭縄文遺跡) 新池から流れた川は、特養老人ホームのところで傍示川に合流する。 傍示川の源流は星田南星台の住宅地を抜け、地獄谷へと遡る。  なすび谷に石組み、一部セメントで築かれている用水路は星田新池がつくられた明治から昭和のはじめ頃に作られたもの思われる。
いずれにしても最近のアニメ映画「千と千尋の神隠し」を思わず連想するような谷筋だ。
なすび谷の滝の下に、家ぐらいの大きな「なすび石」があった。江戸時代の絵図に真っ黒な大きな「なすび石」が描かれているが、今は無い。30個ばかりに砕かれて各家の庭石と化したらしい? この世の世界ではない、あの世の世界、草木が一本とてない荒涼たる様は三途の川の光景が想像される場所を地獄と呼ばれる。
ここ星田の地獄谷は、この谷を歩いた人は、谷が深くて狭く、その深い谷を歩いていると一種異様な雰囲気になり、一刻も早く抜け出たい衝動に駆られる。
なにか陰気な、居てもたってもいられない気分になります。はじめて一人で歩いていたら、途中で引き返すでしょう。なにかゾクゾクする感じがする谷筋だった。だから人のあまり立ち寄らない、村人の恐れられた場所として忌み嫌うので、昔から死牛馬等の捨て場所ともなっていたようだ。
そのような地域であるので「地獄」という地名が生まれたものと思われる。
|
 |
| なすび石の滝(別名・聖の滝)の前で記念撮影 |
 |
 |
 |
|
| なすび石の滝(別名・聖の滝とも言う) 10mを超す素晴らしい滝、涼風が吹き疲れた身体を癒してくれる |
|
 |
 |
| 本日の案内をお願いした 大屋さんと和久田先生 |
用水路?の跡、立派な石組みが 5段、6段と築かれている |
 |
 |
| 大きな石がごろごろと転がっている | 墓石?とも見られる石が右手に見える |
 |
 |
| 感触の良い緑色に苔むした堤跡? | 星田新池の周りを下る |
 |
| 星田の中心部と枚方市 手前の大きな池が星田大池、面積が3.9ヘクタールと交野市で一番大きい池 池の1/3が埋め立てられ交野3中のグランドになっている (滝の直ぐ上に案内して頂き、展望の良い所から撮影した) |
|
2003.7.26(土)天候、曇りのち晴。梅雨明け?の中、沢山の方々が参加された。参加者22人。交野ドームを9時過ぎ車に分乗して出発、星田会館で和久田先生と落ち合い、星田の「なすび石の滝」をご案内頂いた。
星田会館は、妙音池のうえに建てられており、池の築造年代は不明であるが、星田の池の中では最も古く、新宮山の放生池としてつくられたと伝えられている。また、池の中に島があって、弁財天を祀っている。 《ミニガイド》 星田大池 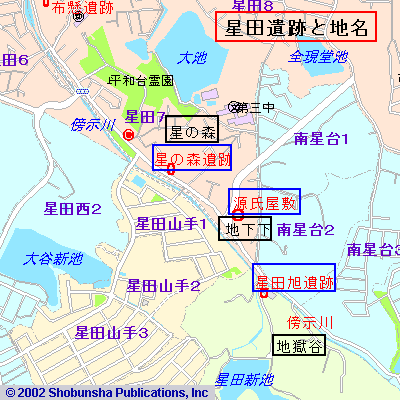 面積が3.9ヘクタールと交野市で一番大きい池である。池の1/3が埋め立てられ交野3中の敷地になっている。 元の面積は6ヘクタールほどあった。星田大池は高岡と楯石・梶ヶ坂の丘陵に挟まれた広い谷地を高い堤防を築いて堰止めして造られた人工の池である。いつ頃築造されたかは不明であるが、古記録によると、元禄11年(1698)に堤防の改修を行っているので、相当古くから出来ていたことになる。 源氏屋敷 源氏の一統星田氏が地下下に住んでいた所を、源氏屋敷という。 「源姓、星田次郎右衛門正種は、河内国星田庄から起こる。家紋丸に三星、水車。千姫取次役、後江戸に帰る」 千姫の取次役として大阪城に出仕し、元和元年(1615)大阪落城のとき、城を脱出して江戸に帰った千姫に随行した武士の中に、星田次郎右衛門正種がいた。 現在は星田山手線が新しく開通して、傍示川の手前の信号付近である。 星田旭遺跡 大谷橋から傍示川を上流へ1キロばかり行くと、茄子石(なすびいし)の谷と沸底(ぼって)の谷から落ちる谷川と、地獄谷の谷川とが一つに集まるところ、小字旭といって両方の谷川に挟まれた麓の小さな台地に、縄文時代の中期、今から4千数百年前から人が住んでいた。 大正の初め、星田新池が築造されたとき、川に近い山麓で十数個の竪穴式住居跡が発見された。この住居跡からは、貝殻に入れた約2000年前の中国の新の時代の青銅貨が発掘されている。また、新池の中に沈んでいる山の崎あたりから和同開珎入りの壺が出土した。 現在は老人ホームが建っている。 《ミニガイド》 星田地区・地名の由来 そのほかの小字名についてはこちらを参照ください。
|