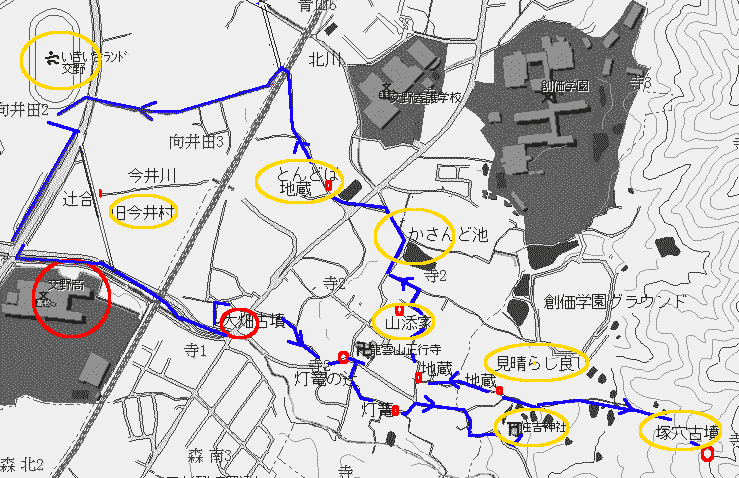|
2003.11.22(土)第57回の参加者は、21名。少し冷え込んだが秋晴れに恵まれ、沢山の方の参加で賑やかになった。特に今回は、明日の交野ロータリーとの協賛による「交野の歴史再発見ウォーク」の下見も兼ねて歩くこととなり、ロータリーの実行委員の安養寺さんが特別に参加され、本番で使われる資料などを頂戴した。
午前9時、平田さんより本日及び明日のウォークの日程などについて説明を受けた後、グランドの観覧席に移動して早速に井戸会長より目の前に広がる交野連山を見ながら、交野の歴史再発見の講義を拝聴した。
9時30分過ぎ、寺古墳群を目指して、いきいきランド交野ドームをスタート。
府道久御山線を南に歩き、トンネルをくぐり交野高校前に出て、旧今井村の田圃を見ると、つい1ヶ月前には、黄金色の田圃であったが、すっかり刈り取られ切り株だけが残っていた。山から吹いてくる秋風が心地よい。交野高校の北で、交野東車塚古墳の発掘当時の様子など、説明を受ける。昭和47年、交野高校が建設されることになり、事前に試掘され発見された。他では類例のない四隅が四角の周溝を有する円墳、「日の丸古墳」が見つかり話題になったことなど。
JRの高架をくぐり寺村に入るところに、弥生時代後期の遺物が出土した住宅地の上が最近の調査で、前方後円墳であることが確認された。墳長90〜95m、後円径50m高さ3m、前方部約50m高さ4mが確認された。これが大畑古墳である。
灯篭の辻で、二月堂、愛宕山、柳谷観音の伏拝を眺めながら当時の村人たちの生活に思いを廻らした。静かな寺の町並みを通り、いつもは真っ直ぐ住吉神社へ上がるが、途中で右折して不断余り通らない道を山に向って上がると綺麗に紅葉した山が見え、段々畑の長閑な風景に出合った。思わず歓声をあげる。交野にもこんな風景がまだまだ残っているのだと、嬉しくなる。
細い道を下り、住吉神社へと出た。住吉神社の神域は、全体にどこか厳かな感じがし、ここは古墳ですよとも言われた。特に本殿の奥に、一人で上ると気持ちのいいものではない。周りには池があり、古墳を造る為に掘ったものではないか、それが、今では灌漑用に利用されていると。境内からは子供たちが遊んだという、「くぼみ石」が次々と見つかった。
住吉神社の南側に綺麗な棚田が見える。ここには、的場という地名が残っていて、毎年正月8日に「お弓」という収穫を占う行事があったそうだ。その的をこの田に立て、住吉神社の所から矢を射て、的に矢が何本突き刺さるかで、その年の収穫の豊凶を占ったという。
住吉神社の北側に出て、山に向かって右折して真直ぐ東に上り、創価学園の小公園を北に見ながら登ると小さな池が左右に5個ほど続き、谷筋を右へ曲がるとさらに池があり、しばらく竹薮と雑木の平地を行くと古墳に出会う。ここが寺塚穴古墳である。 横穴式石室を完全に残す古墳。この周りには、竜王山の山麓に群集する後期古墳群(六世紀から七世紀初頭、飛鳥時代)があり、14基の古墳が、いくつかの尾根に2〜3基づつ点在し、広い範囲をこえて寺古墳群と呼ばれている。 横穴式石室を完全に残す古墳。この周りには、竜王山の山麓に群集する後期古墳群(六世紀から七世紀初頭、飛鳥時代)があり、14基の古墳が、いくつかの尾根に2〜3基づつ点在し、広い範囲をこえて寺古墳群と呼ばれている。
住吉神社の北側の綺麗な棚田は、市内を見下ろす絶好の場所である。また、創価学園の小公園は、桜の名所でもある。直ぐ下に、重要文化財の山添家の大きな萱葺きの屋根が見える。山添家5代孫秀隆は、南伊勢五郡の領主であったが、織田信長に敗れてここに住みつかれたという。
山添家は代々庄屋を勤めた家で、棟札より宝永2年(1705)前後に建てられたことが判っている。間取りは、田の字型をした四間取りに、奥座敷が突き出して造られたのが特徴で、屋根は寄棟造の萱葺きです。
次いで、かさんど池から「とんど場地蔵」にお参りして、旧今井村の田圃道をゆっくりと歩き、いきいきランドへ帰った。
古代の史跡をめぐり寺の町並みを歩き、連綿と続いてきた歴史の一端を肌で感じた楽しい歴史ウォークでした。 次回が楽しみである。一人でも多くの市民の方々にこの喜びを味わっていただきたいと思います。 是非とも、皆さん誘い合って参加しましょう!!!
【寺の地名と古墳ミニガイド】
的場 : 住吉神社の南の段々状の水田になる。寺では毎年正月八日に「お弓」という収穫を占う行事がある。その的をこの田に立て、住吉神社の所から矢を射るのである。的に矢が何本突き刺さるかで、その年の収穫の豊凶を占うのであろう。的場は「お弓」の行事に使用される的を立てた場所を呼んでいる。

八幡木(はちまんぎ) : 南川に沿って寺から私部に出る道がある。道から東で少し入った所に「八幡燈籠(はちまんとうろう)」がある。この燈籠は伏拝神(ふしょうがみ)のことで、八幡宮を祭っている。八幡宮に参る代わりにこの燈籠を拝むことで、八幡宮にお参りするのと同じ効果があった。交野から八幡は北に当たるので村の北に向いて拝むのである。
寺には、この伏拝神の燈籠や碑が他の村に比べて特に多く感じられる。
正行寺の灯篭の辻などには、二月堂、愛宕山、秋葉山、柳谷観音などが見受けられる。昔は、その場所にお参りするのがほとんどできなかったため、村の中で直接拝めるものを求めたのである。
上山田(かみやまだ)、中山田(なかやまだ):竜王山の山ろく崖下の斜面を段々状に切り開いてつくられた開墾地である。住吉神社の北側に当たり、垣内と同じくみごとな階段状の耕地(水田)が広がっている。 田圃のあぜ道に可愛らしい地蔵さんが祀られ居ていていつも、綺麗なお花が生けられて大事にされている。
晴れた日にここから眺める風景は素晴らしい。
垣内(かいと):将来耕地にしようとする予定の土地を垣で囲った地域をいう。
上町、中町、浦町:寺の場合、かいがけ道の入り口にある住吉神社から南川橋に通じる道路の南側、南川に面する部分に上町、中町、浦町ができている。その北側の一段高い面に高い方から、上出垣内、中出垣内、下出垣内の集落が立地している。だから、寺の集落の発展段階は、上町、中町、浦町が最初に形成され、その出垣内として北側に接して形成されたことを物語っている。向垣内は一番遅れて形成されたことを示す。
垣内には集落がない。これは乳母川・(南川)の斜面を切り開いて畑地化するためにできた開墾地である。
後に乳母川の水を引くことができて水田に変わったことで、今はみごとな段々状の水田が開けている。
古墳ミニガイド
《交野東車塚古墳》 交野車塚古墳配置図はこちら
東車塚古墳は交野市南野10番地にある。現在の府立交野高校の校地内と北側の古墳群を言う。 昭和47年、交野高校が建設されることになり、事前に試掘され発見された。5世紀初頭から6世紀頃の5基の古墳群からなる。
交野東車塚南古墳は、他では類例のない四隅が四角の周溝を有する円墳、「日の丸古墳」と言われる。北辺27.5m、南辺26.5m、東辺27.4m、西辺28.8m、その中央に直径22.4mの円墳。
また、東車塚古墳は、5世紀初頭の時期のものと考えられており、周辺域でも確認例のない前方後方墳(墳長65m、後方部の高さ約6m、後方部幅33.5m)で、筒型銅器・巴形銅器・石製腕飾類など多数の遺物が出土している。中でも、単甲は襟付三角板革短甲と呼ばれるタイプの一領で、全国でも20例ほどしか出土していない。
《寺古墳群》
寺古墳群は寺の集落の東南、竜王山の山麓に群集する後期古墳群(六世紀から七世紀初頭、飛鳥時代)である。14基の古墳からなり、いくつかの尾根に2〜3基づつ点在し、広い範囲をこえて寺古墳群と呼ばれている。
そのひとつの寺中山古墳群は、寺の集落を過ぎ、住吉神社の手前の道を真直ぐ東に上り、創価学園の小公園を北に見ながら登ると小さな池が左右に5個ほど続き、谷筋を右へ曲がるとさらに池があり、しばらく竹薮と雑木の平地を行くと古墳に出会う。
これは横穴式石室を完全に残す古墳である。
東西12m、南北11mの方墳で入り口は西を向いている。周りは竹薮と雑木で薄暗い。
大人一人がやっと這って入れる程の入り口から、懐中電灯を片手にした平田さんに続いておそるおそる入る。羨道は短く片袖式となっている。中は、意外と天井が高く、195cmあるという。しっかりと石組みがされている。大きい岩石とそれを支える小さい石が左右にバラス良く組まれている。天井の岩石もしっかりと組まれすこぶる頑丈に出来ている。
|










 横穴式石室を完全に残す古墳。この周りには、竜王山の山麓に群集する後期古墳群(六世紀から七世紀初頭、飛鳥時代)があり、14基の古墳が、いくつかの尾根に2〜3基づつ点在し、広い範囲をこえて寺古墳群と呼ばれている。
横穴式石室を完全に残す古墳。この周りには、竜王山の山麓に群集する後期古墳群(六世紀から七世紀初頭、飛鳥時代)があり、14基の古墳が、いくつかの尾根に2〜3基づつ点在し、広い範囲をこえて寺古墳群と呼ばれている。