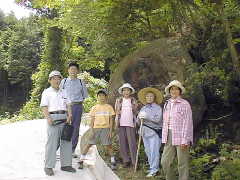|
2002.11.23(土)、参加者は、18名。歴史ウォーク始まって以来の盛況ぶりだった。
何時ものように8時45分頃、噴水広場前に行くと、11月の文化祭で熱心に聞いたり見たりして頂いた数人の方々がウォークに参加されるため集まっておられた。平田さんが当日の歴史ウォークの歩くコースのことなどを説明されているところへも、また数人の方々が顔を出されて総勢18名となった。3日間の文化祭で、歴史ウォークのことをチラシや新聞のコピーなどをお渡しして、PRした効果が出たようだ。何時も参加している常連組みに加えて、10名の新しい方々が参加された。
午前9時15分過ぎ、晩秋の石仏の道を目指して、いきいきランド交野ドーム噴水前をスタート。
府道久御山線を渡り、私部墓地へと歩き、墓地を北へと横切り、青山の田圃道に入る。周りは田圃と畑が広がり、見晴らしが良い。200mも進むと右側に、小さな「かゆ池」と出会う。右手に進むと、私部大池。
その向こうに見えるのは、交野のシンボル・交野山。今日も、われわれを見守っていて下さる、ありがたい山である。交野山はどっしりと座って交野をお守りして頂いている。本当に有り難いことです。
※私部の大池(おいけ)
(故奥野平次さんはふるさと交野を歩く・ひろい話に次のよう述懐されている)
私は「どんでん(水泳)」と言う言葉を聞いただけで、子供の頃の夏が目の前にとんで出る。住んでいた位置から大池に行くことが多かった。7月から8月一杯、天気の良い時は毎日であった。喉(のど)の下の皮をつまんで引くと、それで「どんでん」に行こうかと友達を誘うサインになっていた。思い出してみると、12歳くらい(6年生位)が一番盛んやったと思う。
昔は今と違って大池の東側は北から南まで大きな松が茂っていたので、みんな松の枝を飛び込み台のかわりとしてよく池の中へ飛び込んだものであった。 |
元の道まで大池から引き返し、 北へ進むと第2京阪国道予定地を横切る。青いフェンスで囲まれた道路予定地は、つい最近まで葦?や雑草が繁り、野鳥の格好の棲処(すみか)になっていたが、数メートルの展望台が建ち、土を掘る重機が入り、発掘作業が始まっている。幾筋もの溝らしき跡が発掘されている。 北へ進むと第2京阪国道予定地を横切る。青いフェンスで囲まれた道路予定地は、つい最近まで葦?や雑草が繁り、野鳥の格好の棲処(すみか)になっていたが、数メートルの展望台が建ち、土を掘る重機が入り、発掘作業が始まっている。幾筋もの溝らしき跡が発掘されている。
巨大な道路の建設で交野の素晴らしい自然が壊されるのではと心配されている。野鳥や虫達も何処へ行ったのだろうか?その間も、交野山は静かに見守っておられるのだ。
JR学研都市線を渡り、神宮寺の静かな村の中を歩き、辻のお地蔵さんにお参りする。辻を東に入り、住宅地を通り過ぎ、左に藪、左右にみかん畑を見ながら山道を登ると、右側に東面して花崗岩の自然石に刻まれた弥勒菩薩(第一石仏)がある。この弥勒菩薩は坐像で、右腕を前に出してまげ、掌を外側に開き、左手は組んだ膝の上で掌を下に向けておいて、くつろいだお姿でおられる。
リアルで緻密な線刻描画は、大阪随一の秀作と評され、鎌倉初期の作と言われる。
まわりは竹薮に囲まれ、しっとりとした趣はいつまで眺めていても飽きない。
山裾の藪(神宮寺の宮跡)のある北から里のかけて、奈良時代に開元寺と言う大寺が建ち、その寺が鎌倉時代の頃に、交野山の山頂に寺を移し岩倉開元寺と名を変えたといわれており、この道は岩倉開元寺への参道であった。往時、沢山の僧やお参りする人々が通った道である。
この道が石仏の道である。この石仏の道に存在する弥勒仏坐像石仏、三尊磨崖石仏、阿弥陀如来立像石仏、阿弥陀三尊磨崖石仏、二尊石仏の5点が、平成14年9月1日付けで「廃岩倉開元寺関係石仏群」として交野市の指定文化財になった。
弥勒菩薩から、さらに第一の山池を右下に、第二の山池を左に見て進むとぐっと南に山道は曲がるが、ここからすぐ右側に大石の頂部が見える。この大石の上部中央に南面して、半円の光背に阿弥陀三尊(第二石仏)が刻まれている。
本尊は阿弥陀坐像、脇侍は観音・勢至の両菩薩の立像で、文明11年(1475)と彫られている。室町中期である。現在、交野山への登山道(石仏の道)は、この磨崖仏の北側を通っているが、昔は南側の小川に沿って、眼の上に阿弥陀三尊を拝みながら「なんまいだ、なんまいだ」と唱えながら登ったと言う。 見落としがちなので、要注意。
道の左手に、頭部が少し欠けた阿弥陀さんがおられる。阿弥陀如来立像石仏である。石仏の頭部右半分や光背の上部を欠損しているが、衣は通肩で来迎印を結んでおられ制作年代は室町時代とされている。石仏のある北側斜面は「鳩が谷」とも呼ばれ、以前ここから骨壺が出土したといい、開元寺の墓地であった可能性があり、この石仏も墓地に伴う供養のために造立したと考えられている。
この山道を更に、登ると左に傾いた大石がある。その上部切り込みの光背の中に阿弥陀三尊(第三石仏)が刻まれている。
高さ3mほどの花崗岩に、仏の高さ40cmの本尊阿弥陀如来が蓮華座に坐し、これよりやや下側の両脇には、第二石仏同様、観音菩薩と勢至菩薩の二仏が蓮華座の上に立っている。また、第二石仏同様に室町期の作といわれている。
右側の菩薩が赤茶けているのは、開元寺の火災の時のものともいわれている。
雨上がりの朝、こもれびが射す頃の石仏の美しさを皆さんも是非ご鑑賞下さい。きっとご満足されるでしょう。 近いうちに、是非とも石仏の道をお尋ねください。
再び石仏の道を下り、神宮寺の住宅街を抜け、東倉治の雇用促進倉治宿舎前を通り、JR学研都市線をわたって、源氏池に出た。池は水が抜かれ少なくなった水の中を、養殖の鯉が赤い背びれを見せてゆうゆうと泳いでいた。桜の葉っぱがすっかり落ち冬支度の免除川を歩き、いきいきランドへと帰った。
交野の古い歴史を肌で感じた、楽しい歴史ウォークでした。
次回がまた楽しみである。一人でも多くの市民の方々にこの喜びを味わっていただきたいと思います。
是非とも、皆さん誘い合って参加しましょう!!!
尚、交野市指定文化財(廃岩倉開元寺関係石仏群)の詳細は、交野広報(9/10号)、交野市文化財だより(第10号2002.11.1)をご参照下さい。
|








 北へ進むと第2京阪国道予定地を横切る。青いフェンスで囲まれた道路予定地は、つい最近まで葦?や雑草が繁り、野鳥の格好の棲処(すみか)になっていたが、数メートルの展望台が建ち、土を掘る重機が入り、発掘作業が始まっている。幾筋もの溝らしき跡が発掘されている。
北へ進むと第2京阪国道予定地を横切る。青いフェンスで囲まれた道路予定地は、つい最近まで葦?や雑草が繁り、野鳥の格好の棲処(すみか)になっていたが、数メートルの展望台が建ち、土を掘る重機が入り、発掘作業が始まっている。幾筋もの溝らしき跡が発掘されている。