|
2004.3.27(土)、午前9時京阪電車郡津駅前に集合。 23名の参加で賑やかに郡津の町の地名を尋ねて歩いてきました。郡津駅前に交野の都・郡津の謂れが産経新聞社の好意で石碑が立てられている。 23名の参加で賑やかに郡津の町の地名を尋ねて歩いてきました。郡津駅前に交野の都・郡津の謂れが産経新聞社の好意で石碑が立てられている。
その石碑に「次のような和歌が記されており、本日の講師である、中光司先生より詳しくお話を伺うことが出来た。
「うづらなく 交野のみ野の草枕 いく夜かり寝の数つもるらん」
藤原基氏の歌で「続後拾遺和歌集」にあり、旅の感想を歌ったものだ。また、藤原基氏は包丁使いの名人で鯉料理が得意だったようで、徒然草につぎのように書かれている。
「『園別當入道〔藤原基氏、基家の子〕は、雙(さう)なき庖丁者(はうちゃうじゃ)〔料理人〕なり。
郡津駅前付近は、松塚団地が出来てすっかり様相が変わっているが、北川が天野川に流れ込む手前、山崎の西方は、低湿地帯で長淵(ながぶち)と言われていて、ちょっとした大雨が降ると一面湖水に変わり、京阪電車の線路だけが水面に顔を出している光景がよく見られたそうである。長渕、申田(さるだ)の地名があった。
駅の北側の踏切を東へ越えて小川を渡り、少し行ったT字路を左折し北進すると、弘法大師の常夜灯(大峰山講、文政10年、1827年の銘がある)に出会う。今も、地区の皆様が月2回常夜灯のお世話をされて大切に守られている。
常夜灯から北へ進み直ぐ左は、山崎と言われる場所に出る。山崎より東は下っており、天野川を越えて対岸には枚方丘陵、藤田山がある。この辻を東に行くと、こんもりとした緑の森が見える、これが丸山古墳である。
古墳と言われているが、ハッキリしたことは分からないようである。円墳に見えるが西方に前方部があったかもしれないが、横穴らしい石材が見られないそうだ。頂には神様「椿さま」が祭られ、近隣の人々が大事に清掃され保存されている。
東に出て、枚方交野寝屋川線を渡り、郡津で唯一の地道を東に進むと東高野街道に出会う。交野女子学園の裏手付近を「ものきき」「藪の下」などの地名が残っている。
東高野街道を南に進むと、北尾、梅塚の地名があり、東角には「だら池」がある。環濠集落といわれる、郡津の集落形態で一番規模の大きい「中小路」へと案内された。名前のとおり郡津の中央部(郡津二丁目、三丁目)に位置する小字水塔寺の区域で戸数約30戸である。中小路とはどこから付いた名前かはっきりしないが、村の中へ入ってみると実に路地や曲がった道などややこしい。家と家を結ぶ軒下を抜ける路地もある。T字路、遠見遮断の道路、カギ型道路など集落内をくねくねさせている。
郡津の古い集落の町名には、南尾(みなお)、倉山(くらやま)、中島(なかじま)、中小路(なかしょうじ)、茶屋(ちゃや)、北尾(きたお)、西の町(にしっちょ)があった。
今でも郡津区の下の町組機の町名として使われているし、村の人々は依然としてこの町名で村の場所を示しており、新しい何丁目何番と言われてもさっぱり分からないそうだ。

東の口から地蔵の辻を真っ直ぐ南に出て、倉治道を渡り「中島」を通り、郡津神社に着く。白鳳時代長宝寺跡、手水のくぼみ石を確認。昔の子供達が草餅つき遊びをした跡がくっきりと残っている。大きなくぼみで、何代にも亘って、沢山の子供達が競争して遊んだのだろうか。1300年の時の流れをじっくりと味わう。
郡衙跡の米倉が建ち並んでいたという倉山を通り、T字路、遠見遮断の道路、カギ型道路など集落内をくねくね歩いて、明遍寺に到着。境内には僧明遍の数珠掛松や腰掛石がある。古式豊かな鎌倉地蔵や層塔の四方仏、板碑や唐臼地蔵、双体仏、一石五輪など沢山の石仏がある。
帰りは、東高野街道に出て条里制の五条通を通り郡津駅近辺で解散した。
今回の郡津の地名を辿りながらの歴史ウォーク、楽しく歴史が勉強でき、また今回も新しいことに出会うことが出来ました。 講師の中先生有難う御座いました。
 |
 |
郡津駅前で平田さんより
本日のウォークの予定について |
郡津駅前は綺麗に整備されている
産経新聞社の石碑が立っている |
 |
 |
山崎付近 松塚団地が見える
天野川の丘陵を望む丘陵の突端 |
中先生より説明を受ける、山崎付近、
対岸には枚方丘陵、藤田山がある |
 |
 |
丸山古墳に上る、4世紀頃
円墳に見えるが西方に前方部が
あったかもしれない、
横穴らしい石材が見られない |
丸山古墳遺跡の石碑
西方に鏡池、駒ケ池があった
墳墓の堀跡か |

郡津神社で記念撮影
郡津・地名を歩くMAP
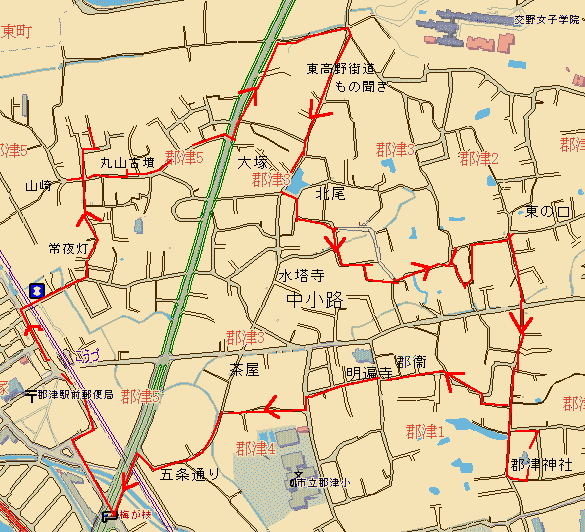

こうづ文化ゾーンご案内看板
京阪電車郡津駅より南300m 府道交野寝屋川線下付近に建てられている
《ミニガイド》
【郡津の名のおこり】
古代、律令体制時代(7世紀後半頃)に、交野郡(かたのごおり)に郡衙(ぐんが)=役所が設けられた。それが現在の倉山の地で、私市から枚方まででとれた年貢米を、当時の長であった郡司さんが、この倉山の倉におさめて管理していた。その周辺に長宝寺という立派なお寺が建てられた。交野で一番古いお寺である。時期は白鳳時代(七世紀後半、約1300年前)。郡津は昔「郡門(こうど)」といった。郡衙(ぐんが)に入る所に門があり「こうど」といった。いつのまにか、「ど」が「づ」にかわり、江戸時代に、こうづの発音どおり「郡津」と改められた。
郡津の村は、環濠集落(かんごうしゅうらく)=【外敵から財産や身を守る村】、と言われている。村から出る所に、東ノ口、西口、西代(にしんだい)などの地名が残っている。防御策として溜池、長池などが利用された。また、台地上に集落があり、谷を防御に村の財産や人の命を守るように作られている。 長宝寺小学校の北側は、春日宮、お出待ち、大門、やぐら池、鳥待ち田など、楽しい歴史的地名が残った土地である。
【郡津の「くらやま」】は、
明遍時から郡津神社にかけて一段高くなった台地を形成しており、この台地に郡司が住み、蔵が建ち、郡司の一族の力で郡衙の東隣の今の郡津神社の場所に長宝寺が建てられていたことが確認されている。 長宝寺址の遺跡の中央には郡津神社の社殿が建てられているが、その周辺から、多くの白鳳時代の瓦片が出土している。
|














